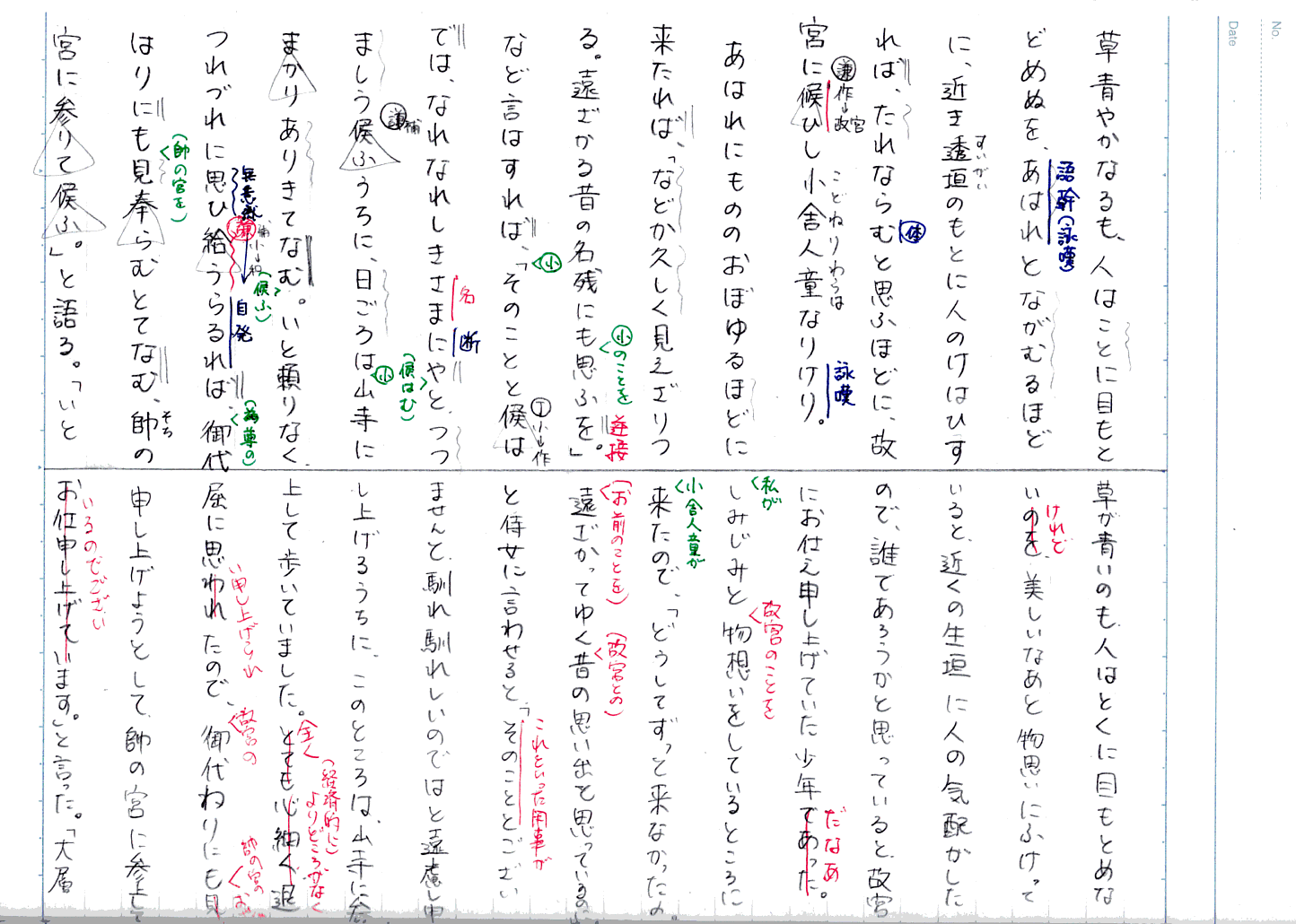
「手かき」とはどういう意味ですか?
しゅ‐しょ【手書】 1 自分の手で書くこと。 また、書いたもの。 2 自筆の手紙。
「かきしぐれ」とはどういう意味ですか?
「柿しぐれ」とは、収穫の1ヶ月程前から柿の実に袋をかけ、固形アルコールで渋を抜いたもの。 関係者の方にお話をうかがったところ、通常の脱渋処理に比べると、一つ一つの実に袋かけ作業を行う手間がかかり、袋かけをするタイミングも10日間程度に限られるため、大量に生産することができないのだそうです。
「かき」の古語は?
かき 【垣・墻】 垣根。 室内に置く仕切りや、建物の間にめぐらす廊下など、垣根に似たもの。
「手」の現代語訳は?
手。 ▽指・手のひら・手首・腕などにいう。 [訳] 指を折って、数えたりなどして。 (器具の)取っ手。
キャッシュ
手鉤の別名は?
手鈎(てかぎ)術 戸隠忍流独特の武器の一つで、木や石垣に登る時に使う。 敵に出会ったときは恐ろしい武器に変わる。 相手の刀を奪って倒す事などから、一刀捕り、白刃捕りとも言われる。
「鉤の手」の読み方は?
かぎ‐の‐て【×鉤の手】
「かき載せる」の古語は?
かき-す・う 【舁き据う】
(輿(こし)や駕籠(かご)などを)かついで来て、しっかりと置く。 [訳] 舟に、牛車(ぎつしや)をかついで来て(乗せ)しっかりと置いて。
「かき離れる」の古語は?
かけ-はな・る 【掛け離る】
遠く離れる。 遠ざかる。 疎遠になる。 大きく隔たる。
手鉤棒とは何ですか?
手の代わりに、吊り荷を押す・引く・回すがかんたんに行えるように補助する道具。
「鈎手」の読み方は?
かぎ‐て【×鉤手】 「鉤の手」に同じ。
「かきくどき」の現代語訳は?
かき‐くど・く【掻口説】
〘自カ四〙 (「かき」は接頭語) 自分の心中を相手にはっきりわからせたり、相手を説得するため、くどくどと繰り返し述べたてる。
「くどく」の古語は?
くど・く 【口説く】
繰り返して言う。 くどくどと言う。 恨みがましく言う。
「ついで」の古語は?
ついで-に 【序に】
その折に。 その機会に。
「率る」の古語は?
ゐる 【率る】 伴う。 引き連れる。 連れる。
手鍵の読み方は?
手カギ (てかぎ) 俵、炭俵、叺などの積み換や荷積み搬送に使用した小道具で、重量物の取り扱いを容易にするのに役立った。
手鉤 何に使う?
手鉤類は主に、穀物類が入った袋物の荷役作業に使用されました。 現在は、漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係などで使われています。
「鉤手」の読み方は?
筋力とバランス力を強化する「鉤手(かぎて)の動作」
「心知れる」の古語は?
こころ-し・る 【心知る】
事情を知る。 物事を理解する。 [訳] 事情を知らない人々(=女房たち)は、「(源氏は)なぜ、お独り笑いを」と非難し合っている。
昼寝の古語は?
うたた-ね 【仮寝・転寝】
思わずうとうと眠ること。 仮寝(かりね)。 [訳] ⇒うたたねに…。
「轟く」の古語は?
とどろ・く 【轟く】
あたりに響きわたる。 [訳] やかましく大きな音が鳴り響く。 (胸が)どきどきする。


